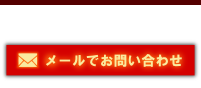課題文38 年功序列型賃金の欠点の一つは、能力のある若い人に対して仕事に見合った報酬が支払われないために、やる気をそいでしまうという点である。
課題文38
年功序列型賃金の欠点の一つは、能力のある若い人に対して仕事に見合った報酬が支払われないために、やる気をそいでしまうという点である。
この文の冒頭に見る「何々の一つは」とくればすぐに思いつくであろう。
“One of 何々”と言う姿を。この「何々」は[欠点]であるから demerit
としてやればよい。当然ながら複数であるからdemeritsである。そこでOne of the demeritsとなり、これが本文の主語である。
そしてこれに「年功序列(seniority)型(system) 賃金(wage) → seniority wage systemがついている。これを前置詞の ofでつないでやればよい。そこで次の図式ができる。
One of the demerits of the seniority wage system is that <能力のある若い人のやる気をそいでしまう> ~
上記に見るように結語の部分、つまり isにつづくのは< >内の一個の文である。従ってそれをつなぐための接続詞の thatが必要になるのはお分かりの通りである。
一個の文である以上、また主語だ結語だ、と騒がなければならない。その主語は「能力のある(talented) 若い(young) 人(people) → talented young people」である。
そしてその結語の動詞は原文では[そいでしまう]であるが、これを言い換えて「失う」とする。主語に合わせるにはそれしかない。loseである。これは他動詞であるから続いてその目的語がこないとならない。それが「やる気」である。Motivationである。
英文ではこれにyoung peopleを指して「彼らの」の theirを補い入れて their motivationとする。これがないと一体だれの「やる気 motivation」なのか分からなくなる。国語はともかく、英文ではこのように所有関係を明確に表示する必要がある。ここで次のようになる。
One of the demerits of the seniority wage system is that talented young people lose their motivation <彼らの仕事に見合った報酬が支払われないために>
上記図式の< >内は、その末尾で言う「ために」から、この文は理由を述べているものと分かる。そこでそれをつなぐ接続詞の because なりsinceを使ってその文をつなぐ。次のように.。
~ because <彼らの仕事に見合った報酬が彼らに支払われない>
上記の< >内の文であるが、その主語は「報酬」としたくなるのであるが、しかしそれには「~ に見合った」などという長い形容がついているので、複雑をきらって「彼らは」を主語としよう。 theyである。
するとその結語の同詞は「与えられない」となる。受身形の否定の姿である。they are not givenとなり、何を与えられないのか、というと「報酬」であるがこの場合は サラリーのsalaryであるが複数の salariesとする。ここで次のようになる。
~ because they are not given salaries <彼らの仕事に見合った>
上記の< >内は名詞の salariesを形容するものである。その形容のためには特に関係代名詞を必要とする。そこでキーワードである。
“サラリーだよ すなわちそれは 彼らの仕事に 見合っているよ”となり、その「は」から関係代名詞 whichを主語として< >内を構成していく
その結語の動詞は「見合う」である。これは「反映する」と言い換えてreflect としたい。他動詞であるからその目的語が「彼らの仕事 → their contribution」となる。そこで結局< >内の形容は which reflect their Contributionとできる。この関係代名詞 which はまた thatにしてもよい。することもできる。
英文
One of the demerits of the seniority wage system is that talented young people lose their motivation because they are not given salaries that reflect their contributions
原文で言う 「と言う点である」 にこだわることはない。
次回予告課題文39
従業員に対する終身雇用制度の最大のメリットは、突然の解雇の心配なしに勤務でき、長期の生活設計ができることであろう。
中野幾雄