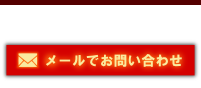課題7 彼はわきの下に本を挟んで歩いている。
日本語での何気ない表現が英訳となると、さてどうしたものかと考える。
まず、自分で課題を英訳し、その後解説を読むようにするよいでしょう。
課題7 彼はわきの下に本を挟んで歩いている。
●基本文
この文に限ることなく、一般に形容の語は全て取り去って最も短い文、
つまり基本文を構成するところから、英文への道筋を見出すことに
するとよい。
●注意
本文の基本は 「彼は歩いている」 である。「歩く」ではなくて(歩いている)と言っている点に注意が向くのである。そうなのだ。
ご存知の「進行形」ということである。
●三人称
そこで先ずは進行形でない姿を構成する。He walksである。主語は第三人称でかつ単数、そして時制は現在形であるから、その結語の動詞には s をつける。規則である。規則は守らねばならない。
●進行形
これを進行形にするのはその結語動詞にingを付して walkingとする。
続いて、そのwalkingの前にbe動詞 isを置いてやればよいのだから
次のような進行形とその英文への構図ができる。
He is walking<わきの下に本を挟んで>
●英文独自の
英文での発想であるが、これは 「本を持って」 と考え、さらにこれを発展させて「本と ともに」とさばく。
するとその 「ともに」 から前置詞の withが頭に浮ぶのは容易であろう。つまり英語ではこのようにものを携行する場合、「ものと ともに」 と言えるのである。我が国語と大いに異なる点である。
●冊数
「本」はbookだからwith a bookとしてやればよい。一冊とみたわけである。複数冊なら with booksとなるところだ。ここで次のようになる。
He is walking with a book <わきの下に挟んで>
●余計な語
上記図式で< >の下線部「挟んで」は正しくは 「挟まれて」 であるが、
しかし わきの下」といっているので、「挟む」 は当然そうなるので、あえて「挟んで → 挟まれて」は不要な、余計な語になるのが英語である。
●英語流
「わきの下」は「腕の下」ということであることに気づきたいのである。
英語流の述べ方である。
●所有関係を明示
そうと気づいたら文句なく under the armである。これはまたunder his armとしてもよい。所有関係をはっきりさせるのが英語の特徴であることを思い出すのである。
英文 He was walking with a book under his arm.
腕の左右別を述べたければ under his right (または left) armとしたらよい。
次回課題8 端のほうに座らずに真ん中に来てください。
中野幾雄