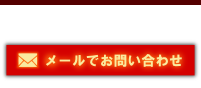課題文49 その動議に25人が賛成投票し、21人が反対投票で3人が棄権したと言われる。
課題文49
その動議に25人が賛成投票し、21人が反対投票で3人が棄権したと言われる。
この文、選挙における投票数に関する表現であり、特殊なので特に注意して、その決まりを理解することが必要である。
一般に 「何々と言われる」 ときたら、その 「と」 の後に続けて 「それは言われる → it is said 」 を置くとよい。つまり「仮主語・真主語」の姿である。
そこで次の図式ができる。
It is said that<25人がその動議に賛成投票した A> <21人がその動議に反対した B> <3人が棄権した C>
上記図式で itを仮の主語であり、that 以降、つまりABCの各文がその it を説明する文となっている。
このように文をつなぐのであるから接続詞の thatが必要となるのはお分かりの通りである。
上記のA文であるが、その主語は「25人」である。「25(twenty five) people」である。これはまた「25 persons」としてもよいが、ここでは peopleを使う。
するとその結語の動詞は 「投票した」 であるからvoteの過去形の votedである。
このように votedとしたら“何々に賛成”のvotedか、あるいは“何々に反対”のそれなのか、いずれかを常に述べることが必要になる。
前者は “voted for 何々”となり、後者は“voted against 何々”となる。つまり「前置詞」で賛成か反対かを区別することが分かるのである。
そしてこの場合の「何々」 は「その動議」であるから“the motion”としよう。「棄権した」は abstainの過去形で abstainedである。その姿は “abstained from 投票 → abstained from voting”となる。
ここでA文は 25 people voted for the motion B文は 21 people voted against the motion C 文は 3 abstained from voting そしてこれらの文が図式どおりに配列されるのであるが、Bとそれ以降におけるA文の繰り返しの語は省略されるから次の英文で完成する。
Cの from votingは繰り返しではないがvoteについてであり、A文とB文とによって分かり切ったことであるから votingは省略され、したがって前置詞のfromも不要となる。
英文
It is said that 25 people voted for the motion, 21 against and 3 abstained.
次回予告課題文50
文字は小さかったが、私は虫めがねの助けをかりて、何とか判読した。
中野幾雄